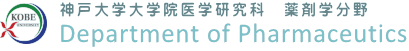研究概要
臨床研究- スペシャルポピュレーション投与設計のためのファーマコメトリクスの応用
- 薬物血中濃度測定による医薬品適正使用に向けての取り組み
基礎研究
-
パーキンソン病発症機構の解明と新規治療薬候補の探索
-
抗がん剤による皮膚色素沈着の予防・治療薬の探索
臨床研究
スペシャルポピュレーション投与設計のためのファーマコメトリクスの応用
スペシャルポピュレーションとは、小児や高齢者、妊婦・授乳婦、腎機能・肝機能低下患者など、薬物動態および薬物感受性が一般の患者集団と異なる特性を有する患者のことです。一方、ファーマコメトリクスとは、数学的な手法により薬物動態を予想する技術を指します。我々は血中濃度を予測することが困難であるスペシャルポピュレーションについて、ファーマコメトリクスを応用することで、適切な血中濃度管理につなげたいと考えております。このことで、これまで予測困難であったスペシャルポピュレーションに対しても適切な薬物投与設計が可能となります。
薬物血中濃度測定による医薬品適正使用に向けての取り組み
治療効果や副作用に関する様々な因子をモニタリングしながらそれぞれの患者に個別化した薬物投与を行うことをTDMといいます。多くの場合、血中濃度が測定され、臨床所見と対比しながら投与計画が立てられます。薬物を投与する際には期待する効果とそうでない効果(副作用)が現れますが、それらが薬物の血中濃度と相関する場合に血中濃度を指標として投与法を決定するわけです。TDMが行われる薬物には一般的な指標として有効血中濃度が知られています。当院では、LC-MS/MSなどの精密機器により種々の薬物血中濃度を測定し、治療効果や遺伝子変異との相関性について検討しています。
基礎研究
パーキンソン病発症機構の解明と新規治療薬候補の探索
パーキンソン病は中脳黒質緻密層のドパミン神経脱落によるドパミン不足により、振戦、固縮、無動などの運動障害を呈する神経変性疾患です。様々な治療薬が開発されていますが、根本的な治療法が存在しません。そこで当研究室ではパーキンソン病発症機構の解明、そして新規作用機序に基づいたパーキンソン病治療薬の探索に焦点を当て研究を行っています。
~パーキンソン病発症メカニズムの解明~
パーキンソン病発症には、加齢や環境、遺伝的素因、ミトコンドリア機能障害等が関与する可能性が報告されていますが、詳細な原因は不明です。一方、近年小胞体ストレス(ER
stress)誘発による神経細胞死がパーキンソン病発症に関与する可能性が報告されています。変性蛋白質の蓄積によって起こるER stressに対して、細胞は蛋白質の翻訳抑制、ERシャペロン誘導による蛋白質折りたたみの促進、そしてユビキチン-プロテアソーム系を介した小胞体関連分解(ERAD)の促進等の防御機構を作動させますが、これらの防御機構でもER
stressが緩和されない場合、神経細胞死が惹起され、パーキンソン病発症に繋がると考えられています。
私たちは、小胞体ストレス関連分子としてユビキチンリガーゼHRD1と安定化分子SEL1Lを同定していますが、最近これらの分子がパーキンソンモデルに対して保護的に働くことを見出しました。そこで、HRD1/SEL1LがPD治療の新たな標的になるのではないかと考え、現在も研究を行っています。
~パーキンソン病の新規治療薬の探索~
パーキンソン病治療は病勢進行を遅らせる対症療法が主であり、根本的治療薬が無いのが現状です。そこでドラッグ・リポジショニングによる新規作用機序に基づくPD治療薬探索を試みています。ドラッグ・リポジショニングは既にヒトでの安全性が確認されている既承認医薬品から、別の疾患に有効な薬効を見つけ、実用化に繋げようとする手法であり、医薬品開発にかかる時間とコストを削減できます。現在までに、オキシカム系NSAIDsがCOX-2非依存的に抗PD効果を示すこと等を見出しました。現在、他の化合物についても探索を進めています。
抗がん剤による皮膚色素沈着の予防・治療薬の探索
がん薬物療法による外見関連副作用に対する支援(アピアランスケア)は、社会生活を続けながら治療を受ける患者のQOLを確保するために重要な支持療法です。がん薬物療法による外見関連副作用は多岐に渡りますが、中でも殺細胞性抗がん剤による「皮膚色素沈着」は、顔や手指に好発し他者からも認知されやすいことから、心理的苦痛を伴う副作用の一つと報告されています。しかし、皮膚色素沈着は生命に関わることは少なく緊急性が低いことから、発症メカニズムに関する研究は進んでおらず、根本的治療薬も見つかっていません。本研究では、殺細胞性抗がん剤による皮膚色素沈着の発症メカニズムの解明および有効な予防・治療薬を見出すことを目的とし、培養細胞を用いたモデル構築や化合物探索を行っています。