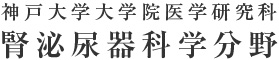アンドロロジーグループ
臨床研究:男性不妊症治療の最前線
不妊症は、約10〜15%のカップルに認められ、その原因の約半数が男性側に起因しています。近年、生殖医療技術の進展により、ART(assisted reproductive technology)を用いた妊娠・出産の成功例が増加しており、男性不妊症治療の選択肢も広がっています。アンドロロジーグループでは、男性不妊症と男性更年期障害を中心に外来診療を展開し、患者一人ひとりの状態に応じた最適な治療法を提供しています。 男性不妊症治療においては、妊娠までの期間や費用対効果を考慮した治療選択が重要です。特に、患者の背景やパートナーの年齢、不妊症の原因に基づいた個別化が求められます。当グループでは、精索静脈瘤に対する内精静脈結紮術や、無精子症に対するmicrodissection TESE(testicular sperm extraction)による精子回収が行われ、これにより挙児の機会が大幅に増加しています。これらの治療法により、従来は不可能とされていた症例でも挙児が可能となり、男性不妊症治療に新たな希望をもたらしています。 しかし、遺伝的要因に関連する症例では、治療後に遺伝的影響が次世代に伝播するリスクについて慎重な検討が求められます。遺伝的リスクを考慮した治療法の選定と、患者への遺伝的カウンセリングを強化しています。 遺伝的背景や内分泌環境に基づく個別化医療を向上させ、患者一人ひとりに最適な治療を提供することを目指し、臨床研究を積極的に行っています。これにより、男性不妊症治療のさらなる革新が期待され、臨床応用に向けた新たな道を切り開いていく所存です。
基礎研究
当グループの基礎研究は、特に、視床下部-下垂体-精巣軸におけるサイトカインや成長因子が精巣機能に及ぼす影響に加え、精巣内でのGerm cell、Sertoli cell、Leydig cell間の細胞間調節に着目した研究を行っており、これまでに多くの成果を上げてきました。 これらの精巣機能調節機構の解明をさらに進めるため、iPS細胞を用いたライディッヒ細胞の作成や、造精機能障害モデルを用いた実験に重点を置いています。これにより、精巣内での遺伝子導入を行い、spermatogenesis(造精過程)や steroidogenesis(ステロイド生成)のメカニズムの解明を目指しています。また、iPS細胞から作成したライディッヒ細胞を用いた基礎研究も進めており、将来的にはこれらのライディッヒ細胞をヒトへ移植することで、分泌される男性ホルモンを用いた男性更年期障害の治療を目指した臨床応用も視野に入れています。 さらに、環境ホルモンや抗がん剤が造精機能に与える影響についても重点的に研究しており、これらの影響を修復する薬剤の開発にも取り組んでいます。特に、環境因子や薬剤が男性不妊症の原因となるメカニズムを解明し、それに対する新たな治療法の開発を目指しています。 これらの基礎研究は、最終的に臨床応用に向けた重要なステップとなり、男性不妊症や男性更年期障害の治療の革新に寄与することを期待しています。