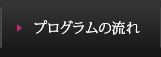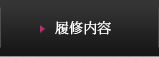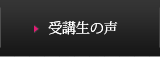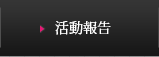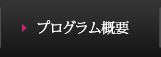生体構造解剖学5年生(取材当時) 柴田 哲希「学び、対話し、新たな世界を視る」
※専攻・学年は取材時のものです。
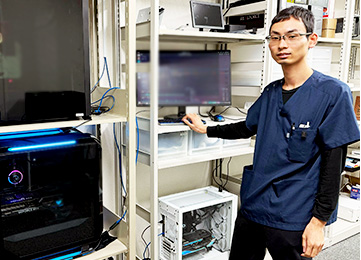
- Q.いつ頃から医学研究コースを履修しようと考え始めたのですか?
またそのきっかけは何ですか? - 医学部に編入学した時点で医学研究には取り組みたいと考えていました。私は編入学で入学し、入学前は情報系企業に開発職として勤務していました。情報学技術を医学に使いたいと思って編入したため研究に取り組みたいと当初から考えていましたが、医学の知識がなく何ができるのかはいまいちわかっていなかったと思います。2年生秋の基礎配属実習で生体構造解剖学分野に配属され、そこで初めて医学研究に取り組み楽しかったため継続して医学研究コースを履修しました。
- Q.この分野を選んだ理由は?
- 細胞内のタンパク質の構造を原子レベルで観察するという当時の自分がこれまで触れたことがなかった技術に魅力を感じて生体構造解剖学分野で研究を始めました。入学前は医学と無関係な分野にいたため、基礎医学でどのような研究が行われているか、まだ理解できていない面もあったのですが、2年生時に同分野の仁田亮先生に声をかけていただき、興味を持ちました。構造生物学が情報学技術も複合して発展してきた分野であったということが魅力に感じた点で、クライオ電子顕微鏡の画像解析や分子動力学法、また近年有名な機械学習による立体構造予測など、関連する分析技術が多くあります。私が興味のある、情報学技術の医学応用という点でも楽しく研究ができています。

- Q.このプログラムの魅力は何ですか?
- 医学研究ということを軸に様々な研究やそれらに関わる人のことを知り、つながりをもてることだと思います。このプログラムに所属していると自分の研究室だけでなく他研究室で研究に取り組む同学・他学の学生や教員とも交流を持つことができる機会が用意されています。こういった機会を通じて医学研究自体について多くのことを学ぶことができたと思いますし、またこのプログラムに所属していなかったら知り合っていなかっただろう学生や教員からも大きな刺激を受けてきました。このプログラムを通じて得たつながりから研究プロジェクトに関わらせていただいたこともあります。
- Q.現在の取り組み、今後の取り組みを教えて下さい。
- 現在生体構造解剖学分野でクライオ電子顕微鏡と分子動力学法を用いて逆行性キネシンというモータータンパク質の移動機構を原子レベルで解明する研究に取り組んでいます。クライオ電子顕微鏡から得られる逆行性キネシンの画像を解析して立体構造を同定し、その立体構造変化から細胞内で分子の移動が生じるメカニズムを解明しました。またクライオ電子顕微鏡ではタンパク質が移動中の不安定な中間状態の解析が困難なため、分子動力学法での物理シミュレーションを使って移動メカニズムに関する仮説の裏付けにも取り組んでいます。この研究は論文として発表する予定です。
加えて他の分野での研究にもいくつか関わらせていただいています。分子疫学分野では西森誠先生のもとで循環器内科領域への機械学習応用として、心電図や胸部X線画像などのマルチモーダルデータから患者の背景病態をモーダル間で共通の高次元空間上に抽出し、検査順序や一部の検査データの欠損に依存せず診断を導くことができる機会学習モデルの開発に取り組んでいます。この研究についても在学中の論文発表を目指しています。また他に臨床分野ではこれまで神戸大工学部と救命救急科との共同研究や腫瘍血液内科の研究などにも参加してきました。今後も機会があればさまざまな分野との研究に関わらせていただければと思います。

- Q.このプログラムに参加し、得たことがあなたの将来にどのように活かされると思いますか?
- 研究で得た経験や知識は将来も研究を継続する上で役に立ちますし、基礎研究の視点は臨床診療に取り組む場合や臨床研究をする上でも役立つと思います。現代の医療は基礎研究の上に成り立っており、研究を通じて得た知識を応用した薬や治療法が臨床現場でも日々使われ、アップデートされているのを臨床実習で実感しています。基礎という大きな土台の上に成り立つ医療の力を最大限引き出すには病態生理や薬の作用機序などの理解は必須であり、基礎研究で得てきた知識も役立っています。また臨床診療で遭遇する症例は教科書の知識やこれまでにわかっている研究だけでは説明できないことも多く、それらに答えるため自分自身でも研究を通して医療の発展に少しでも貢献出来たらいいなと思っています。
- Q.これから履修を考えている学生へ一言
- 医学部での学生生活は講義や試験で忙しいとはいえ、研究や部活動など何に自分の時間を使うかを選びやすいです。学生の身分ならばどれくらい研究に時間を費やすか、といったことも比較的柔軟に決めることができます。研究に興味がある人はぜひ興味がある分野の研究室を気軽に覗いてみてください。