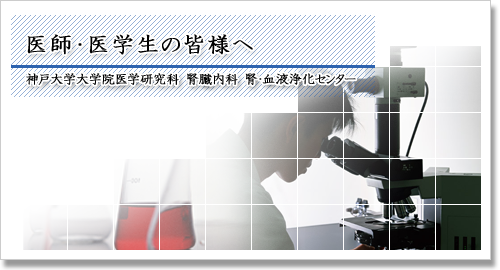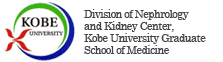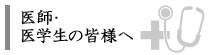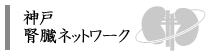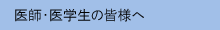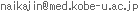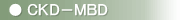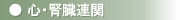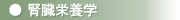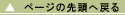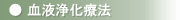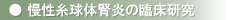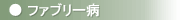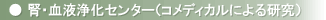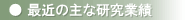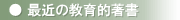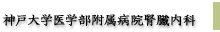日本腎臓学会の疫学調査によると、将来末期腎不全に至る危険性を有する患者慢性腎臓病(Chronic kidney disease:CKD)stage 3以上(推定GFRが60mL/min/1.73m2 未満)は、1098万人存在すると報告されています。このCKDは心血管疾患の発症や死亡の重要な危険因子であり、健康を脅かす重要な症候群と考えられます。
これまでの各種腎炎における組織学的検討のみならず、私たちは酸化ストレスの観点からこのCKDの進行を防げるように、基礎から臨床的研究まで幅広く行っております。
CKD患者では、種々の骨ミネラル代謝異常を生じます。
近年、この種々の骨ミネラル代謝異常が、骨形態への影響のみならず血管石灰化など生命予後・QOLにより大きな影響を及ぼすことが明らかとなり、CKDに伴う全身性の骨ミネラル代謝異常(CKD-Mineral and Bone Disorder:CKD-MBD)として認識されています。
私たちの教室ではCKD-MBDに関して,透析患者の二次性副甲状腺機能亢進症、糖尿病の骨代謝異常を中心に、分子学的アプローチを用いた基礎研究から、多施設共同での臨床研究に至るまで、様々なトランスレーショナルリサーチを進めています。
近年、「心・腎連関」という言葉が盛んに使われるようになっていることからもわかるように、明らかな腎機能の低下が存在しない状態(例えば微量アルブミン尿の存在のみ)でも、腎疾患の存在は心血管系疾患の重要なリスクファクターであることが明らかになっております。私たちは、これらのリスクファクターを減らすべく、心・腎両方の病態を考え、世界レベルの治療および研究を行っている日本では数少ない教室の一つであります。
CKD患者の心血管合併症を減らすために日々絶え間ない努力を重ねております。
医食同源と言われるように食生活と疾患は切り離すことのできない関係です。腎臓は吸収された栄養素から産生された代謝産物などを排泄する主な器官であり、CKDの患者では容易に代謝産物の蓄積や体液の過剰を引き起こすため、厳格な栄養管理(評価)が必要です。
特に保存期腎不全患者においては、低蛋白食と腎保護効果との関係や、透析患者においては低栄養と生命予後との関係が知られております。我々は腎臓栄養学と言う新しい分野での基礎から臨床的な研究まで幅広く行っております。
神大附属病院腎臓内科 研究内容
従来の透析療法ではアルブミン結合性尿毒素の除去は困難であり、慢性透析患者の体内に蓄積し、悪影響を及ぼしていることが推定されてきましたが、測定法が困難なことなどより、明らかにされておりませんでした。私たちは、アルブミン結合性毒素の中のひとつであるインドキシル硫酸に特に注目し、研究活動を行っております。このインドキシル硫酸の透析患者における尿毒素としての働きは、明らかにされておりませんでしたが、私たちが初めて透析患者の副甲状腺ホルモンの骨抵抗性への関与を明らかにし、またCKDでの心肥大進展への関与についても報告しました。
その他全身への影響を現在研究中です。
我が国の世界最先端の繊維化学技術を駆使し、数多くの新しい血液浄化療法が開発さ れています。当院ではこれらの最先端の血液浄化療法の一環として患者さまに最適な血液透析・血液透析濾過療法の検討のみならず、血液・神経・皮膚領域等の難病に対するアフェレシス治療の有用性に関しても、各診療科協力のもと幅広く検討し、その安全性・有効性の評価や世界に発信できるEvidenceの確立を目指し、日々臨床研究を行っております。
当科では毎年約80~100例の腎生検を施行しています。その多くは糸球体腎炎であり、良好な治療成績を得られていますが、いまだ治療に関するエビデンスが十分に確立していない分野も残されています。
われわれの教室では、病理学教室の協力を得て、慢性糸球体腎炎の患者様の病理所見と治療経過を詳細に検討し、よりよい治療プロトコールを確立するための臨床研究を行っております。
ファブリー病では、ライソゾームの中にある酵素(α-ガラクトシダーゼ)が生まれつき不足あるいは欠損しているために、この酵素で分解されるはずのスフィンゴ糖脂質が分解できずに血管壁に蓄積し、さまざまな臓器の障害を来たします。腎臓にも蓄積するとわかっており、腎障害が進行するとやがては透析が必要な状態になります。透析に至った場合でも、この疾患は脳血管障害や心血管障害を引き起こすので、適切な治療が重要となってきます。
我々は兵庫県を中心とした透析患者様、約1000人にスクリーニングを行い、約0.3%の方がファブリー病であることを報告しております。この頻度は世界の報告とほぼ一致する頻度であります。症状は多岐にわたるため診断が難しいケースもあるとされておりますが、できるだけ早期からの酵素補充療法が病状の進行や症状を緩和すると報告されております。我々の教室でもファブリー病の診断、治療を行っており日々研究を進めております。
神大附属病院腎臓内科 研究活動
看護師
主に、透析室における下肢末梢動脈疾患指導、タイムアウト導入による医療安全対策、アクションカードを用いた災害対策などを中心に積極的に取り組んでいる。患者指導から医療安全まで幅広い視点で臨床に直結する看護研究を行っている。
臨床工学技士
光学式非観血的連続ヘマトクリットモニターなどの非侵襲的モニタリングを用いた安全性の高い血液透析療法や、その他の血液浄化療法を中心に研究を行っております。
また、特殊な血液浄化療法についても積極的に取り組んでおります。
英文原著論文のみを掲載しています。過去のものは下記より閲覧ください。
| 2006 年 | 2007 年 | 2008 年 | 2009 年 | 2010 年 |
| 2011 年 | 2012 年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
| 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
【 2024年 】
- Fujii H.
Unravelling the complexities of myocardial injury in patients with chronic kidney disease.
J Atheroscler Thromb. 31(5): 522-523, 2024. - Goto S, Hamano T, Fujii H, Taniguchi M, Abe M, Nitta K, Nishi S.
The benefit of reduced serum phosphate levels depends on patient characteristics: a nationwide prospective cohort study.
Clin Kid J. 17(10): sfae263, 2024. - Goto S, Fujii H, Mieno M, Yagisawa T, Abe M, Nitta K, Nishi S.
The benefits of living kidney transplantation in hemodialysis patients.
Clin Exp Nephrol. 28(2): 165-174, 2024. - Goto S, Hamano T, Fujii H, Taniguchi M, Abe M, Nitta K, Nishi S.
Hypocalcemia and cardiovascular mortality in cinacalcet users.
Nephrol Dial Transplant. 39(4): 637-647, 2024. - Hirabayashi K, Fujii H, Kono K, Yamatani S, Shimizu M, Watanabe K, Sakamoto K, Goto S, Nishi S.
Association of abnormalities in electrocardiography and ultrasonic echocardiography with the occurrence of cardiovascular disease in patients with advanced chronic kidney disease.
Clin Exp Nephrol. 28(4): 307-315, 2024. - Hanafusa N, Abe M, Joki N, Hoshino J, Kikuchi K, Goto S, Kanda E, Taniguchi M, Nakai S, Naganuma T, Hasegawa T, Miura K, Wada A, Takemoto Y.
Annual dialysis data report 2020, JSDT Renal Data Registry.
Ren Replace Ther 10: 14, 2024. - Hyodo T, Hara T, Goto S, Fujii H, Nishi S, Yoshimoto A, Ito T.
Clinicopathological characteristics of neural epidermal growth factor-like 1 protein associated membranous glomerulonephritis.
Virchows Archive. 2024. (in press) - Hyodo T, Hara T, Goto S, Fujii H, Nishi S, Nozu K, Yoshikawa N, Yoshimoto A, Ito T.
Immunohistological analysis reveals IgG1-dominant immunophenotype of tubulointerstitial nephritis unassociated with IgG4-related diseases.
Int Urol Nephrol. 56(7): 2363-2369, 2024. - Murashima M, Fujii N, Goto S, Hasegawa T, Abe M, Hanafusa N, Fukagawa M, Hamano T.
Residual kidney function modifies the effect of cinacalcet on serum phosphorus levels among peritoneal dialysis patients.
J Nephrol. 37(4): 1137-1139, 2024.
※分担執筆を行ったもの、編集を行った著書を含みます。
- レジデントのための腎臓病診療マニュアル 第2版/医学書院
- 透析患者の病態へのアプローチ 改訂2版/金芳堂
- 腎生検プラクティカルガイド/南江堂
- 腎機能を考えた安全な処方/医薬ジャーナル社
- EBM透析療法2010-2011/中外医学社
- 透析患者の検査値の読み方改訂第3版/日本メディカルセンター
- 専門医のための薬物療法Q&A/中外医学社
- 腎臓・水電解質コンサルタント/金芳堂
- 透析療法事典/医学書院
- 慢性腎臓病(CKD)に伴う貧血(ガイドラインサポートハンドブック)
/医薬ジャーナル社 - 慢性腎臓病(CKD)に伴う骨ミネラル代謝異常(CKD-MBD)
(ガイドラインサポートハンドブック)/医薬ジャーナル社 - 血液透析患者における心血管合併症の評価と治療
(ガイドラインサポートハンドブック)/医薬ジャーナル社 - 透析合併症/最新医学社
- 変革する透析医学/医薬ジャーナル社
- 腎疾患治療のエビデンス第2版/文光堂
- AKIのすべて/南江堂
- 第2項 腎疾患作成モデル/エル・アイ・シー
- やさしい透析患者のための血圧と心臓・血管の自己管理
/医薬ジャーナル社 - CKD-MBDハンドブック2/日本メディカルセンター
- 全人力・科学力・透析力・for the people 透析医学/医薬ジャーナル社
- 本日の治療指針/医学書院
- こんな時どうすれば!? 腎移植コンサルタント/金芳堂