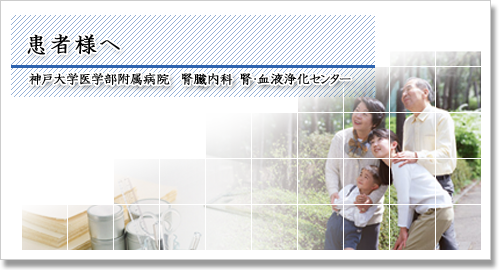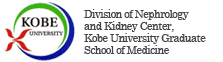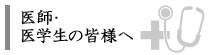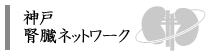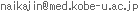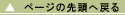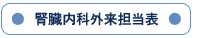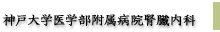日本腎臓学会の疫学調査によると、将来末期腎不全に至る危険性を有する患者[慢性腎臓病(Chronic kidney disease:CKD)stage 3以上(推定GFRが60mL/min/1.73m2 未満)]は、1098万人存在することが明らかになりました。このCKDは心血管疾患の発症や死亡の重要な危険因子であり、健康を脅かす重要な症候群と考えられます。
当科では、健康診断などでみつかる何も自覚症状のない軽度の蛋白尿や血尿の方、むくんでいる方、少し腎機能が低下している方、末期腎不全で透析療法が必要になるかもしれない方、さらには高血圧、糖尿病、膠原病など全身の病気による腎障害の方まで、腎臓に関するほとんどの病気をカバーしています。また、特殊な病態として、水・電解質異常、尿路結石等の診療も行っています。さらに、長期透析療法に伴う合併症の診断や治療、血液浄化療法の必要な患者さまの血液浄化療法のプランニングも行っています。
→ 外来担当表
神大附属病院腎臓内科 診療内容
蛋白尿・血尿の方
学校や職場の検診にて蛋白尿や血尿を指摘された方は、将来末期腎不全(透析療法が必要となる状態)にいたる可能性が高いので、検診の結果を放置しないで必ず腎臓内科の外来を受診してください。
外来にて診察および各種検査(血液および尿検査、腹部超音波などの画像診断)を行ない、その原因が腎疾患によるものと考えられた際に、腎生検による精密検査をすすめていきます。
腎生検は、約 1 週間の入院を必要とし、通常月曜日、水曜日あるいは木曜日に超音波ガイド下で行ないます(年間約 80~100 例)。採取した組織より確定診断を行い、当科のカンファレンスにて治療方針を決めます。その内容について、担当医より十分な説明をさせていただき、患者さまに十分理解いただけるよう配慮しています。
腎機能低下の方
慢性腎臓病の原因は、糖尿病性腎症、慢性腎炎症候群、腎硬化症、多発性嚢胞腎など様々であり、当科ではその原疾患の特殊性や患者さまの個々の状態を考慮し、慢性腎臓病の進行を抑制出来るように治療を行なっております。
特に慢性腎臓病治療の中で重要な位置を占める食事療法ですが、当院栄養科の管理栄養士とともに、個々の患者さまに合わせた繊細な栄養指導を行えるよう配慮しております。原則として患者さまに 24 時間蓄尿を行っていただき、蛋白・塩分摂取量などを評価しております。薬物療法の効果を十分に発揮できるよう指導を行なっておりますが、約 2 週間前後の入院の上、食事療法の強化および心血管系疾患の精査なども行っております。
また、当院では毎月腎臓病教室を開催しておりますので、参加ご希望の方は外来担当医とご相談ください。
末期腎不全で透析療法が必要と言われた方
近い将来透析療法が必要と言われた慢性腎不全の患者さまに対し、患者さまご自身のライフスタイルに適した治療法(透析療法あるいは移植療法)を可能な限り選択できるよう配慮しております。このような治療は腎代替療法と呼ばれ、当院では腎代替療法の適切な情報提供を行うために、毎週木曜日午後に専任看護師による腎代替療法説明外来を行っております。
移植療法を希望された患者さまに、実際に腎移植の手術を行う泌尿器科への紹介を行い、腎移植の適否およびレシピエント(腎臓受給者)の術前検査とドナー(腎臓提供者)の選定および評価を行います。腎移植までに末期腎不全のための腎代替療法が必要となった場合は、その間透析療法を行います。
透析療法を希望された患者さまには、適切な時期に必要な準備を行わせていただきます。血液透析の場合は、内シャント設置術を行います。約 1 週間前後の入院を必要とし、院内中央手術室にて局所麻酔下で行っております(年間約 50 例)。また、腹膜透析の場合には、当院にてカテーテル挿入術を行い、腹膜透析導入を行っております。
患者さまの検査結果や尿毒症症状などの全身状態を評価した上で、透析療法が必要と判断された適切な時期に透析療法を開始(導入)いたします。
血液透析療法導入(開始)後全身状態が安定した時点で、患者さまのご自宅近隣の施設にご紹介いたします。(当院では外来維持血液透析は行っておりません。)
長期透析療法に伴う合併症の診断や治療の必要な方
日本透析医学会統計調査委員会の報告によりますと、2012 年 12 月 31 日現在、慢性透析をされている患者さまの数は約 309,946人であり、これは国民 464.4人に一人の割合であり、年々増加傾向にあります。このことは透析技術の進歩に伴い、長期間にわたる安定した維持透析が可能となった今日、透析療法を受ける患者さまにおけるactivities of daily living(ADL)やquality of life(QOL)などの生活の質の改善が重要となっています。
透析期間が長くなるにつれ、このADLやQOLの低下をきたす合併症が、多かれ少なかれ発生してくるのも事実です。当科では、シャントトラブル、カテーテル感染、二次性副甲状腺機能亢進症、悪性腫瘍、心血管系疾患、消化管出血などの合併症に対して、それぞれの該当する診療科と連携し、それらの合併症の予防・診断・治療に取り組んでいます。
血液浄化療法の必要な方
血液浄化療法とは、病気の原因(あるいはその病気の原因に関連している)物質が血液中に存在すると考えられる病気において、血液からこれらの物質を直接除去したり、あるいは欠乏している物質を血液中に補充したりすることによって病気を改善させる治療法です。具体的な適応疾患として表に示すようなものがあげられます。これらの疾患を専門に診療する診療科と連携をとりながら、院内の「腎・血液浄化センター」にて治療を行います。
なお現在、保険適応疾患に対して加療中の患者さまは、かかりつけの先生を通してご相談ください。なおこれらの「血液浄化療法」が適応となる疾患におきましても、治療をうけるにあたっていくつかの満たす条件があります。
二次性副甲状腺機能亢進症で副甲状腺摘除術が必要な方
透析の重要な合併症の一つとして二次性副甲状腺機能亢進症が挙げられます。
これは骨の異常をきたすこと、血管をはじめとした石灰化を促進させること、また、痒み、痛み、イライラ感などの症状に関係すると言われております。二次性副甲状腺機能亢進症に対して、当院の耳鼻咽喉科と連携して副甲状腺摘出術を行っています。術前の評価や術後の内科的管理は、当科で行っています。
この治療は、食事制限や薬物治療などを十分行っていても、リン、カルシウム、副甲状腺ホルモンのコントロールがつかなくなっている方が適応となります。特にリンが高い状態が続くと、心血管系疾患が増加することが知られており、適切な治療が必要です。
多発性嚢胞腎で腹部症状が強い方
多発性嚢胞腎は、遺伝性に腎臓にたくさんの嚢胞という袋が発生し腎臓が次第に大きくなる病気です。嚢胞が大きくなるとお腹が張るようになったり、食事が一度に多くとれなくなる場合があります。また、嚢胞からの出血による血尿や嚢胞への感染を繰り返すこともあります。
このような患者さまの嚢胞を縮小させ症状を改善する治療法として、手術で腫大した腎臓を取り去ることも一つの選択肢ですが、手術ではなく、腎臓を栄養する血管にカテーテルによって詰め物をする腎動脈塞栓術という治療法が有効であることが報告されております。当院では、放射線科と連携をとりながらこの腎動脈塞栓術を行っております。
ファブリー病の疑いまたは診断を受けられた方
ファブリー病では、生まれつきα-ガラクトシダーゼという酵素が不足あるいは欠損しているために、この酵素で分解されるはずの糖脂質が分解できずに血管の壁に蓄積し、さまざまな臓器に障害を来たします。腎臓にも蓄積するとわかっており、やがては透析が必要な状態になります。透析に至った場合でも、脳や心臓の血管に障害を引き起こすことが知られており、適切な治療が重要となってきます。
症状は多岐にわたるため診断が難しいケースもあるとされておりますが、できるだけ早期からの酵素補充療法が病状の進行や症状を緩和すると報告されております。当科でもファブリー病の診断、治療を行っております。
神大附属病院腎臓内科外来案内
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
後藤(俊)、 藤田・菊田 |
後藤(公)、田渕 | 藤井、平井 | 岡本 | 河野 |
| 専門外来 | |||||
| 午後 | 川勝 | 寺田 | 藤井 | 後藤(俊) | 坂本 |
| 移植外来 |
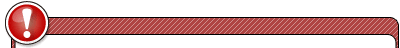
※ 初診の方は、午前 11 時までにご来院ください。
午後は再診のみです。
※ 学会等で担当医が変更になっていることもありますので、
ご了承ください。
※ 初診の方は神戸大学医学部附属病院ホームページを
ご参照ください。
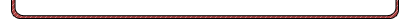
神大附属病院腎臓内科 診療担当医
腎・血液浄化センターでは保険適応疾患に対して、血液透析(hemodialysis:HD)、腹膜透析(peritoneal dialysis:PD)、血液透析濾過(hemodiafiltration:HDF)、血液濾過(hemofiltration:HF)、血漿交換(plasma exchange:PE)、二重膜濾過法(double filtration plasmapheresis:DFPP )、直接血液吸着(direct hemoperfusion:DHP)、エンドトキシン吸着療法(PMX)、血漿吸着(plasma adsorption:PA)、LDLアフェレシス(LDL-A)、白血球吸着除去療法(leukocytapheresis:LCAP)、顆粒球吸着療法・顆粒球除去療法(granulocytapheresis:GCAP)など様々な「血液浄化療法」を行っております。
当センターは腎臓内科医を中心とする医師だけでなく、当センター専任看護師および臨床工学技士が力を合わせ、高度なチーム医療を目指しています。
なお当センターは原則として、当院に入院されている患者様のみの対応となっております。
| 年 | HD | その他の 血液浄化 | 合計(回) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 1809 | 159 | 1968 |
| 2004 | 1658 | 98 | 1756 |
| 2005 | 1458 | 143 | 1601 |
| 2006 | 1936 | 173 | 2109 |
| 2007 | 2224 | 144 | 2368 |
| 2008 | 3124 | 142 | 3266 |
| 2009 | 3078 | 135 | 3213 |
| 2009 | 3078 | 135 | 3213 |
| 2010 | 3007 | 108 | 3115 |
| 2011 | 3533 | 242 | 3775 |
| 2012 | 3473 | 233 | 3706 |
| 2013 | 3278 | 193 | 3471 |
| 2014 | 3716 | 161 | 3877 |
| 2015 | 3947 | 285 | 4232 |
| 2016 | 4166 | 221 | 4387 |
| 2017 | 3977 | 229 | 4206 |
| 2018 | 4359 | 230 | 4589 |
| 2019 | 4015 | 272 | 4287 |
| 2020 | 3421 | 242 | 3663 |
| 2021 | 2649 | 220 | 2869 |
| 2022 | 3347 | 201 | 3548 |
| 2023 | 3717 | 260 | 3977 |
| 2024 | 3711 | 233 | 3944 |
【シャント・腎生検件数】
| 年 | シャント手術 | PDカテーテル 挿入術 | 腎生検 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 52件 | 50件 | |
| 2009 | 40件 | 82件 | |
| 2010 | 52件 | 87件 | |
| 2011 | 36件 | 98件 | |
| 2012 | 55件 | 91件 | |
| 2013 | 46件 | 79件 | |
| 2014 | 50件 | 76件 | |
| 2015 | 58件 | 93件 | |
| 2016 | 44件 | 93件 | |
| 2017 | 54件 | 107件 | |
| 2018 | 44件 | 76件 | |
| 2019 | 43件 | 92件 | |
| 2020 | 41件 | 6件 | 81件 |
| 2021 | 41件 | 4件 | 82件 |
| 2022 | 43件 | 3件 | 71件 |
| 2023 | 33件 | 8件 | 83件 |
| 2024 | 38件 | 8件 | 59件 |