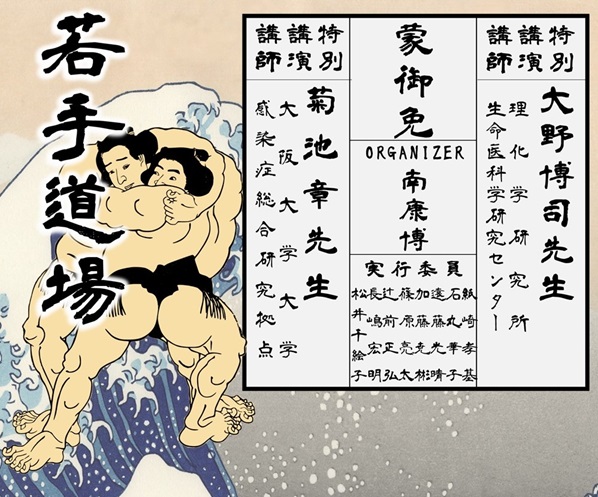本講演はオンラインにて医学研究先端講義「先端医学トピックス」としても開催されます。
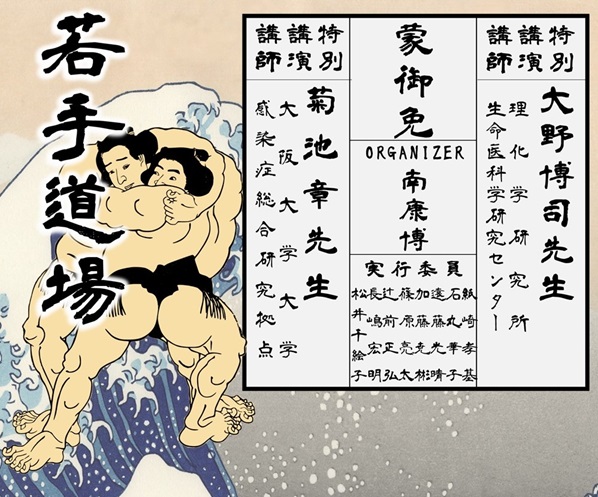
(KEYNOTE 1) 10月10日(木)16:00~17:00
菊池 章 先生
大阪大学感染症総合教育研究拠点 特任教授
Lessons from Experiments ~神戸大学医学部で学んだこと~
Lessons from Experiments ~Lessons gained from my time at Kobe University School of Medicine~
私は1982年に神戸大学医学部を卒業後、内科臨床医を経て1988年に生化学教室の助手となりました。それ以来、神戸大学、UCサンフランシスコ、広島大学、大阪大学と異動しながら基礎医学研究を行ってきました。1995年に独立するまでは低分子量GTP結合タンパク質を介する細胞機能制御に関する研究を、独立してからはWntシグナルによる細胞機能制御とその異常による病態に関する研究を展開してきましたが、研究への向き合い方は神戸大学時代に学んだことがその礎になっています。
この40年間に各種分野の技術が爆発的に進歩し、政治、経済、社会の考え方が大きく変化する中で、科学研究に求められることも変わってきたことを実感しています。しかし、それでも、新たなことを知りたい、新しいことに挑戦したいという研究者の気持ちの根本は変わっていないと信じています。本講演では、これまで研究を通して学んだことをご紹介しながら、生物学、生命科学、医学研究の変遷と今後の展望を皆様と共有し、討論したいと思います。
|
(keynote 2) 10月10日(木)17:10~18:10
大野 博司 先生
理化学研究所生命医科学研究センター(IMS)副センター長
粘膜システム研究チーム チームリーダー
宿主ー腸内細菌相互作用
Host-gut microbiota interaction
ヒトを含む動物の腸管には40兆個以上にも及ぶ腸内細菌叢が存在する。
腸内細菌叢は、われわれの健康や疾患と密接に関わっている。
近年のメタゲノム解析や無菌マウスを用いた研究から、種々の疾患でみられる腸内細菌叢のバランスの異常、
dysbiosisは疾患の結果ではなくむしろその発症や増悪の原因となり、
このdysbiosisを是正してバランスを正常な状態、
すなわちsymbiosisに戻してやることが治療や予防に繋がることが明らかとなりつつある。
我々は、網羅的ゲノム配列解析であるメタゲノム解析に加え、
網羅的遺伝子発現定量解析(トランスクリプトーム)、
網羅的代謝物定量解析(メタボローム)など、
異なる階層の網羅的解析を組み合わせた統合オミクス手法により、
宿主-腸内細菌叢相互作用の分子メカニズムの理解を試みてきた。
本講義では、腸内細菌叢が宿主の生体防御・免疫系、疾患にどの様に関与しているかについて
解説する。
|