R5年度CMX国際共同研究短期派遣・招へい事業報告
|
パリシテ大学(仏)Lariboisière Hospitalへの派遣
 この度、メディカルトランスフォーメーション研究センター「国際共同研究短期派遣・招へい事業」により、フランスパリシテ大学に派遣されました(派遣期間:2023年8月26日〜31日)。フランス滞在期間中、パリシテ大学脳神経外科よりワークショップを開催いただき、当研究室(松本教授、木村)、神戸大学脳神経外科学教室(藤本助教)、パリシテ大学脳神経外科(Emmanuel Mandonnet教授、研修医1名)、フランス国立情報学自動制御研究所(Inria)(François Bonnetblanc主任研究員、博士研究員1名、院生2名)が参加しました。 日本からは電気生理学的脳活動の指標である皮質皮質間誘発電位に関して、検査手法(刺激パラメータが電位に及ぼす影響)や解析結果(高周波数解析など)を、フランスからは脳外科手術に用いる脳内ネットワーク評価法や、白質刺激のシミュレーションモデルと誘発脳電位の解析方法を提示し、時間をかけてディスカッションを行いました。また、実際に手術室で脳腫瘍切除術を見学し、手術で用いる白質刺激の手法と解析方法を学びました。 今回フランス現地で対面での討議を行うことで、皮質・白質の刺激方法と計測すべきパラメータについて、詳細かつ円滑な議論を進めることができました。  |
ボルドー大学(仏)神経変性疾患研究所への派遣
 この度、CMX国際共同研究短期派遣・招へい事業により、ボルドー大学に派遣いただきました(2024年3月18日〜24日)。滞在期間中の主目的として、大脳基底核研究で著名なThomas Boraud博士を訪れ、依存症の病態メカニズム解明に関する共同研究をどのように進めていくかについて議論しました。Boraud博士は、パーキンソン病患者における脳深部刺激術の臨床応用、またその作用機序の解明を最初に行った大脳基底核研究の第一人者です。私は、Boraud博士と10年以上前から交流があり、これまで学会のシンポジウム共催や大脳基底核研究に関する意見交換を行ってきました。 今回、初めてボルドー大学を訪れ、これから申請する国際グラントに関する具体的な研究立案を行ってきました。また、ボルドー大学には、Boraud博士の他、Nicolas Mallet博士やJérôme Baufreton博士など、国際的な大脳基底核研究者が多数おり、それぞれと非常に長時間のディスカッションも行うことが出来ました。私の研究もセミナーという形で時間を与えていただき、討論できたことは非常に有意義でした。 今回の渡航により、国際グラントの採択が実現されれば、さらに嬉しく思います。 |
|
チューリッヒ大学(スイス)Medical Informatics/Biomedical Image Analysisへの派遣  2024年4月から始まる国際共同研究に先立ち、神戸大学・京都大学とスイスのチューリッヒ大学の共同研究準備のため3月にチューリッヒ大学を訪問しました。この研究の目的は、チューリッヒ大学の多言語対応LLM技術と日本の高品質な医療情報を融合し、日本語に対応した高精度なLLMを開発することです。 今回の訪問では、1.データ収集、2.データ前処理、3.LLMの基礎構築、4.LLMの学習、5.オンプレミス環境構築、6.LLMの改善、7.LLMの性能評価という7つの研究段階に基づく密な技術交流と意見交換が行われました。特に、日本語医療情報対応LLMの構築やオンプレミス環境でのLLM稼働、多タスク対応性能の検討が中心的な課題として議論されました。 訪問中にはチューリッヒ大学側の研究室がスイスの国家プロジェクト「AI initiative」に参加しており、月2万時間の計算資源が確保されていることが確認されました。また、両者の協力により、医用画像を用いたLLMの研究が大いに進展することが期待されています。ただし、個人情報保護の観点からデータ共有のハードルが高いことも認識され、今後の課題として検討される予定です。 今回の訪問により、信頼関係が構築され、今後の共同研究に向けた基盤が整ったことに感謝しております。 |
|
パジャジャラン大学(インドネシア)Department of Pediatric Medical Facultyからの招へい 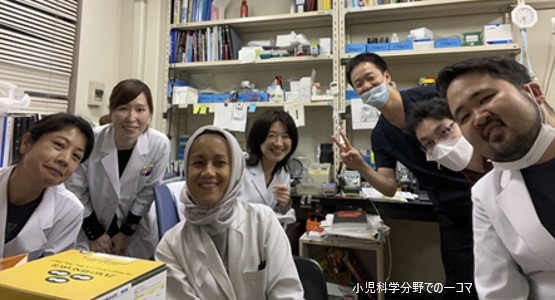 この度、CMX 国際共同研究短期派遣・招へい事業のご支援により、2024年2月3日~19日の間、インドネシアのPadjadjaran大学からRini Rossanti先生を招へいさせていただきました。Rini Rossanti先生は以前、神戸大学大学院博士課程(小児科学)においてネフローゼ症候群を中心とした小児遺伝性腎疾患に関する研究に従事され、2022年に学位取得後、インドネシアで小児腎臓医として勤務されながら、研究を続けてこられました。 Rini Rossanti先生は、日本における研究経験を活かし、インドネシア内で小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の遺伝学的診断体系を確立することを目指しており、まずは共同研究という形で、当科のバックアップのもとインドネシアの小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群に対する、次世代シークエンサーを用いた網羅的遺伝子解析を行うこととしました。滞在期間中24例分の解析を実施し、5例で遺伝子異常を同定することができました。今後さらに症例を増やし、インドネシアで解析を実施できるよう準備をすすめている段階です。 今回の招へい事業により、共同研究を進めることができました。このような機会を与えて下さったことに心より御礼申し上げます。 |
|
ハーバード大学(米)医学大学院からの招へい
 2024年3月に米国ハーバード大学から吉良信一郎博士を招聘するにあたり、本事業より支援を受けました。当分野では以前より、VR技術を活用したマウスの社会行動実験と脳神経イメージングに取り組んでいます。そこで、VR行動課題を用いた神経科学研究に長けている吉良博士との共同研究を進めることで、さらに研究を発展させることを目指しました。 滞在中、CMXセミナーを通じて、マウス用VRによる空間ナビゲーション課題や二光子カルシウムイメージング、光遺伝学操作実験の知見を深めることができました。また、当分野とハーバード大学のVR実験システムを比較検証しました。吉良博士からは、実験プラットフォームにおけるトレッドミルの動きの効率的なセンシング技術の導入など、VRシステムの改善について貴重なアドバイスをいただきました。今回の取り組みは、VRシステムによる社会ナビゲーションにおける脳機能の理解を深めるための基盤となるものであり、今後の研究として光遺伝学操作を組み合わせた実験系構築につながりました。 また、吉良博士には当分野の若手教員や大学院生と1対1で時間をかけた議論を行っていただきました。そこでは研究内容そのもののアドバイスだけでなく、海外での研究の取り組みやキャリアパスの重要性などを若手スタッフは学ぶことができたようで、非常に実り多き機会となりました。 |