沿革
医学部の前身は、兵庫県立神戸医科大学であり、その母体は兵庫置県と共に建設された神戸病院です。
明治、大正、昭和と県政の歩みの中に幾多の変遷、消長を経て、昭和43年(1968年)3月31日に国への移管が完了し、神戸大学医学部となりました。
医学部の歴史は、この附属病院の歴史でもあり、現在では関西における医学・医療の中心的役割の一翼を担うようになっています。
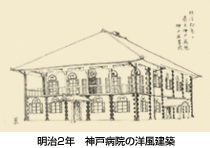
医学研究科・医学部の歴史
| 明治2年 | 4月 | 神戸病院が創立、同院内に医師養成場(医学伝習所)を設置 |
|---|---|---|
| 明治9年 | 医学伝習所を神戸病院附属医学所と改称 | |
| 明治10年 | 2月 | 神戸病院を公立神戸病院と改称 |
| 明治15年 | 4月 | 県立神戸医学校を設置 |
| 12月 | 公立神戸病院を県立神戸病院と改称 | |
| 明治16年 | 4月 | 県立神戸医学校附属薬学校を設置 |
| 明治17年 | 2月 | 同附属薬学校を県立薬学校と改称 |
| 明治21年 | 3月 | 県立神戸医学校、同薬学校が廃校 |
| 昭和19年 | 4月 | 県立医学専門学校が設置され、県立神戸病院が県立医学専門学校附属医院と改称 |
| 昭和21年 | 4月 | 県立医科大学の設置(19講座、入学定員80人)。 |
| 昭和24年 | 4月 | 県立医科大学附属高等看護学院The Nursing School attached to the Hyogo Prefectural College of Medicineを設置 |
| 昭和26年 | 3月 | 県立医学専門学校を廃止 県立医科大学予科を閉科(学制改革)。 |
| 昭和27年 | 2月 | 県立神戸医科大学を設置 県立医科大学附属医院を県立神戸医科大学附属病院と改称 |
| 4月 | 神戸医科大学の開校式を挙行 | |
| 昭和28年 | 4月 | 附属科学捜査研究所を附属法医学研究所と改称 |
| 生理学第二講座及び精神神経科学講座を設置 | ||
| 旧制研究科を設置 | ||
| 昭和29年 | 4月 | 病理学第二講座及び整形外科学講座を設置 |
| 昭和30年 | 1月 | 医学進学課程を兵庫農科大学及び姫路工業大学に設置 旧制学位審査権が附与される。 |
| 4月 | 解剖学第二講座を設置 | |
| 昭和32年 | 4月 | 衛生学公衆衛生学講座を廃止、衛生学講座及び公衆衛生学講座を設置 |
| 9月 | 附属法医学研究所その他を統合し、附属研究所に改変 | |
| 昭和33年 | 3月 | 県立神戸医科大学大学院医学研究科(博士課程)を設置 |
| 12月 | 大学本館等竣工 | |
| 昭和34年 | 4月 | 附属高等看護学院に保健学科を増設し、県立厚生女子専門学院に改称 |
| 昭和35年 | 5月 | 附属研究所を附属成長機構研究所と改称 |
| 昭和36年 | 3月 | 旧制県立医科大学、旧制研究科を廃止 |
| 昭和37年 | 4月 | 皮膚泌尿器科学講座を廃止、皮膚科学講座及び泌尿器科学講座を設置 |
| 7月 | 附属図書館竣工(443坪) | |
| 昭和38年 | 3月 | 実験動物舎竣工(211坪) |
| 12月 | 閣議において県立神戸医科大学の昭和39年度国立移管が決定 | |
| 昭和39年 | 4月 | 神戸大学に医学部が設置され、県立神戸医科大学の国立移管を開始 医学進学課程全部、専門課程1年次、基礎医学10講座が移管 |
| 昭和40年 | 1月 | 産業医学講座を廃止、医動物学講座を設置 |
| 4月 | 国立移管第2年度として、基礎講座3講座、臨床講座5講座が移管 | |
| 昭和41年 | 4月 | 国立移管第3年度として、臨床講座5講座が移管 |
| 昭和42年 | 4月 | 大学院医学研究科(博士課程)を設置 |
| 国立移管第4年度として、大学院生全部、臨床講座3講座及び附属図書館が移管 | ||
| 6月 | 県立神戸医科大学附属病院及び県立厚生女子専門学院は、国立移管に伴い、神戸大学医学部附属病院及び同附属看護学校と改称 | |
| 麻酔学講座を設置 | ||
| 昭和43年 | 3月 | 国立移管完了により神戸医科大学及び神戸医科大学大学院を廃止 |
| 4月 | 学部学生入学定員が100人となる | |
| 昭和44年 | 3月 | 医学部共同研究館竣工 |
| 4月 | 内科学第三講座及び脳神経外科学講座を設置 附属衛生検査技師学校を設置(入学定員20人)。 |
|
| 昭和47年 | 4月 | 附属衛生検査技師学校を附属臨床検査技師学校に改組 |
| 昭和48年 | 3月 | 附属衛生検査技師学校を廃止 |
| 4月 | 生化学講座を生化学第一講座に改称。生化学第二講座及び放射線基礎医学講座を設置 | |
| 学部学生入学定員が120人、大学院学生入学定員が54人となる。 | ||
| 附属動物実験施設を設置 | ||
| 昭和51年 | 2月 | 基礎学舎(新営第1期工事)竣工 |
| 昭和52年 | 3月 | 基礎学舎(新営第2期工事)竣工 |
| 昭和53年 | 3月 | 附属看護学校及び附属臨床検査技師学校の校舎竣工(須磨区友が丘7丁目10) |
| 8月 | 附属看護学校及び附属臨床検査技師学校の名谷地区への移転が完了 | |
| 昭和54年 | 3月 | 基礎学舎(新営第3期工事)竣工 |
| 4月 | 附属医学研究国際交流センターを設置 | |
| 口腔外科学講座を設置 | ||
| 昭和55年 | 4月 | 放射線施設を設置(部局内措置) |
| 共同研究施設を設置(部局内措置) | ||
| 昭和56年 | 10月 | 神戸大学に神戸大学医療技術短期大学部を併設 |
| 昭和58年 | 4月 | 情報センターを設置(部局内措置) |
| 昭和59年 | 4月 | 附属看護学校を廃止 |
| 昭和60年 | 4月 | 附属臨床検査技師学校を廃止。臨床検査医学講座を設置。 |
| 昭和63年 | 4月 | 老年医学講座を設置 |
| 平成元年 | 4月 | 学部学生入学定員が100人となる。 |
| 平成3年 | 4月 | 医学部及び附属病院の事務部を統合し、医学部事務部(総務課、管理課、学務課、医事課)に改組 |
| 平成6年 | 10月 | 医学部保健学科を設置(入学定員160人)。 |
| 平成8年 | 4月 | 災害・救急医学講座を設置 |
| 7月 | 管理棟竣工 | |
| 平成10年 | 3月 | 神戸大学医療技術短期大学部を閉学 |
| 4月 | 学部学生入学定員が95人となる(平成12年度より学士入学制度の導入)(3年次編入;入学定員5人)。 | |
| 6月 | 臨床研究棟竣工。保健学科校舎竣工。 | |
| 平成11年 | 4月 | 大学院医学研究科が大学院医学系研究科に改称。 大学院医学系研究科保健学専攻(修士課程)を設置 |
| 平成12年 | 4月 | 大学院医学系研究科内科学専攻に連携講座放射光医学を設置(学内措置) |
| 平成13年 | 2月 | 神緑会館竣工 |
| 4月 | 大学院医学系研究科保健学専攻(博士後期課程)を設置 | |
| 大学院医学系研究科生理学専攻等5専攻が医科学専攻に改組 | ||
| 大学院医学系研究科医科学専攻に基幹講座として9大講座、35教育研究分野、4協力講座(12教育研究分野)及び3連携講座(3教育研究分野)を設置 | ||
| 医学部医学科35講座を廃止し4大学科目となる。 | ||
| 大学院医学系研究科医科学専攻に連携講座映像粒子線医学を設置(学内措置) | ||
| 平成14年 | 4月 | 大学院医学系研究科医科学専攻に連携講座発生・再生医学を設置(学内措置) |
| 大学院医学系研究科バイオメディカルサイエンス専攻(修士課程)を設置(入学定員20人) | ||
| 平成16年 | 4月 | 国立大学法人へ移行 |
| 附属医学研究国際交流センターを附属医学医療国際交流センターに改組 | ||
| 大学院医学系研究科医科学専攻に臨床薬効評価学講座を設置(学内措置)(〜21年3月) | ||
| 医学部事務部管理課を経営管理課に改称 | ||
| 7月 | 大学院医学系研究科医科学専攻に立証検査医学講座を設置(学内措置) | |
| 平成18年 | 1月 | 大学院医学系研究科医科学専攻にへき地医療学を設置(学内措置) |
| 4月 | 大学院医学系研究科に人材育成センターを設置(部局内措置)(〜25年2月) | |
| 平成19年 | 4月 | 大学院医学系研究科医科学専攻を次のように改めた。 ■基礎医学領域:生理学・細胞生物学講座,生化学・分子生物学講座,病理学・微生物学講座,社会医学講座 ■臨床医学領域:内科学講座,内科系講座,外科講座,外科系講座 |
| 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座超微構造生物学,感染・免疫学,リハビリテーション運動機能学を設置(学内措置) | ||
| 大学院医学研究科医科学専攻連携講座映像粒子線医学を粒子線医学,分子イメージング学(〜令和2年3月)に改編(学内措置) | ||
| 平成20年 | 4月 | 大学院医学系研究科を大学院医学研究科に改称。医学研究科医科学専攻を次のように改めた。 生理学・細胞生物学講座、生化学・分子生物学講座、病理学講座,微生物感染症学講座、社会医学講座、内科学講座、内科系講座、外科学講座、外科系講座 また、連携講座感染症フィールド学、システム病態生物学、こども発育学(〜25年3月)を設置 |
| 大学院医学研究科に質量分析総合センターを設置(部局内措置) | ||
| 大学院保健学研究科保健学専攻を設置 | ||
| 医学部事務部経営管理課を管理課,病院経営企画課に再編 | ||
| 6月 | 大学院医学研究科医科学専攻にリウマチ学を設置(〜24年3月) | |
| 10月 | 大学院医学研究科医科学専攻に不整脈先端治療学を設置(学内措置) | |
| 11月 | 共同研究館改修及び寄附建物竣工 | |
| 平成21年 | 4月 | 医学部附属動物実験施設を医学研究科附属動物実験施設に改組 |
| 医学部附属医学医療国際交流センターを医学研究科附属感染症センターに改組 | ||
| 大学院医学研究科医科学専攻に機能・画像診断学(〜令和2年3月),美容医科学(〜24年3月)を設置(学内措置) | ||
| 医学部医学科の入学定員が100名となる。 | ||
| 6月 | 社会医学講座を地域社会医学・健康科学講座に改称 | |
| 10月 | 大学院医学研究科医科学専攻にこども急性疾患学を設置(学内措置) | |
| 平成22年 | 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻のへき地医療学をプライマリ・ケア医学に改称(学内措置)(〜27年3月) |
| 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座病態脳科学(〜29年3月),病態分子細胞生物学(〜29年3月),新規治療探索医学(〜令和4年5月)を設置(学内措置) | ||
| 医学部医学科の入学定員が103名となる。 | ||
| (3年次学士入学制度を2年次学士入学制度に変更) | ||
| 大学院医学研究科バイオメディカルサイエンス専攻(修士課程)の入学定員が25名となる。 | ||
| 平成23年 | 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座 生体機能分子応用学(〜30年3月),規制科学を設置(学内措置) |
| 大学院医学研究科にトランスレーショナルリサーチ・イノベーションセンターを設置(部局内措置)(〜28年3月) | ||
| 医学部医学科の入学定員が105名となる。 | ||
| 医学部事務部に研究支援課を設置 | ||
| 平成24年 | 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻にリハビリテーション機能回復学を設置(学内措置) |
| 大学院医学研究科に先端生体医用画像研究センター(〜令和2年3月),コラボレーションセンター(〜27年3月)を設置(部局内措置) | ||
| 医学部医学科の入学定員が108名となる。 | ||
| 医学部事務部に施設管理課を設置 | ||
| 5月 | 大学院医学研究科医科学専攻に泌尿器先端医療開発学を設置(学内措置) | |
| 10月 | 大学院医学研究科医科学専攻に分子代謝医学を設置(学内措置) (〜令和4年3月) | |
| 大学院医学研究科にグローバルリーダー育成センターを設置(部局内措置)(〜29年3月) | ||
| 平成25年 | 1月 | 大学院医学研究科医科学専攻に病態シグナル学を設置(学内措置) |
| 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻に地域連携病理学を設置(学内措置) | |
| 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座 小児先端医療学,小児高度専門外科学を設置(学内措置) | ||
| 医学部医学科の入学定員が110名となる。 | ||
| 5月 | 大学院医学研究科に膜生物学・医学教育研究センターを設置(部局内措置)(〜28年3月) | |
| 平成26年 | 2月 | 大学院医学研究科に医療機器・再生医療製品レギュラトリーサイエンスインキュベーションセンターを設置(部局内措置)(〜29年3月) |
| 4月 | 医学部に地域医療活性化センターを設置(部局内措置) | |
| 大学院医学研究科にメディカルイノベーションセンターを設置(部局内措置)(〜28年3月) | ||
| 大学院医学研究科医科学専攻に病理ネットワーク学を設置(学内措置) (〜令和5年3月) | ||
| 医学部医学科の入学定員が112名となる。 | ||
| 平成27年 | 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻に地域医療支援学、こども総合療育学を設置(学内措置) |
| 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座循環器高度医療探索学、心臓血管外科先端医療学を設置(学内措置) | ||
| 7月 | 大学院医学研究科にWHHLMIウサギ開発・供給・研究センターを設置(部局内措置)(〜30年3月) | |
| 11月 | 大学院医学研究科医科学専攻に低侵襲外科学を設置(学内措置) | |
| 平成28年 | 4月 | 大学院医学研究科にシグナル伝達医学研究展開センターを設置(部局内措置) (〜令和4年3月) |
| 平成29年 | 4月 | 医学部に国際がん医療・研究センターを設置(〜31年2月) |
| 大学院医学研究科医科学専攻に国際がん医療・研究推進学を設置(学内措置) | ||
| 大学院医学研究科にテニュアトラック推進センターを設置(部局内措置) | ||
| 大学院医学研究科に次世代国際交流センターを設置(部局内措置) | ||
| 大学院医学研究科医科学専攻(博士課程)の入学定員が100名となる。 | ||
| 医学部事務部に患者サービス課、国際がん医療・研究センター事務室を設置 | ||
| 平成30年 | 2月 | 医学部に統合型医療機器研究開発・創出拠点を設置(部局内措置) |
| 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻に健康創造推進学(〜令和6年3月)、脊椎外科学、先進救命救急医学を設置(学内措置) | |
| 平成31年 | 3月 | 医学部附属国際がん医療・研究センターを医学部附属病院に再編 |
| 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻に先進医用画像診断学を設置(学内措置) | |
| 医学部に臨床解剖トレーニングセンターを設置(部局内措置) | ||
| 令和元年 | 7月 | 大学院医学研究科医科学専攻に先進代謝疾患治療開発学を設置(学内措置)(〜令和4年6月) |
| 8月 | 大学院医学研究科医科学専攻にAI・デジタルヘルス科学分野を設置(学内措置) | |
| 令和2年 | 1月 | 大学院医学研究科医科学専攻に放射線医工学を設置(学内措置) |
| 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座精神疾患高度医療探索学を設置(学内措置) | |
| 令和3年 | 2月 | 大学院医学研究科にこころの疾患研究センターを設置(部局内措置) |
| 4月 | 大学院医学研究科にプレシジョン・テレサージェリーセンターを設置(部局内措置) | |
| 大学院医学研究科医科学専攻に関節温存・再建外科学,足病医学を設置(学内措置) | ||
| 医学部事務部患者サービス課を医療支援課に改称 | ||
| 6月 | 大学院医学研究科に難治性がん研究センターを設置(部局内措置) | |
| 10月 | 大学院医学研究科にデジタルイノベーション推進センターを設置(部局内措置) | |
| 令和4年 | 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻に生体シグナル制御学を設置(学内措置) |
| 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座難治性網膜視神経変性治療学を設置(学内措置) | ||
| 大学院医学研究科にメディカルトランスフォーメーション研究センターを設置(部局内措置) | ||
| 6月 | 大学院医学研究科医科学専攻に新規治療探索医学を設置(学内措置) | |
| 11月 | 大学院医学研究科医科学専攻に未来医学講座を設置(学内措置) | |
| 令和5年 | 4月 | 大学院医学研究科医療創成工学専攻(博士課程前期課程,博士課程後期課程)を設置(入学定員 博士課程前期課程15人,博士課程後期課程8人) |
| 医学部に医学教育推進センターを設置(部局内措置) | ||
| 医学部事務部に医療創成工学事務室を設置 | ||
| 8月 | 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座先端感染症制御学を設置(学内措置) | |
| 10月 | 大学院医学研究科に疾病健康管理・疫学研究センターを設置(部局内措置) | |
| 令和6年 | 4月 | 大学院医学研究科医科学専攻に連携講座先進循環器画像診断学を設置(学内措置) |
| 大学院医学研究科医科学専攻こども総合療育学を小児神経学・発達行動小児科学に改称 | ||
| 大学院医学研究科医科学専攻(博士課程)の入学定員が120名となる。 |